突然はじまった、家族の介護のカタチ
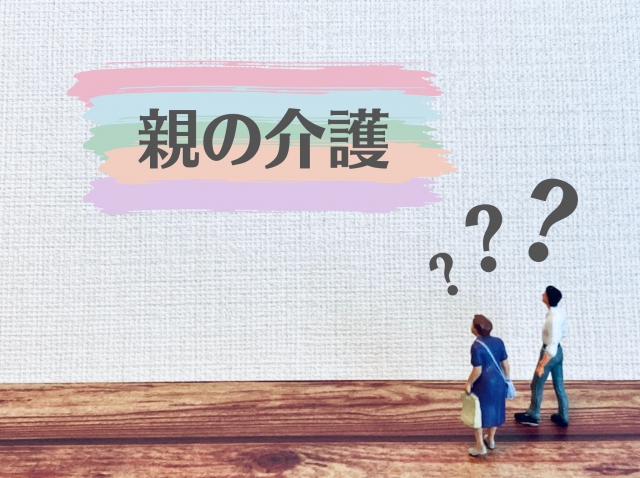
父が倒れたのは、もう6年前のこと。
ほんとうに、突然でした。
「お父さんが救急車で運ばれて、今病院にいる」
そんな連絡を母からもらって、胸がざわざわしたのを覚えています。
まだまだ元気でいてくれると思い込んでたから、
その知らせはまるで現実じゃないみたいで。
でも、現実でした。
父は“脳梗塞”を発症していたのです。
右半身に麻痺が残り、バランスを取る機能もダメージを受けて、
外をひとりで歩くことは難しくなってしまいました。
家の中や施設の中なら、歩行器を使ってなんとか歩けるけれど、
ふらつきがあるので、ちょっと目を離した隙に転んでしまうかもしれない。
そんな不安がつきまとうようになりました。
それから母が中心となって、父の介護がスタート。
いわゆる「介護生活」が始まったんです。
この6年間、
何度か転んでしまったり、
脱水で救急搬送されたこともありましたが、
なんとか落ち着いた状態を保っていました。
でも、半月ほど前にまた突然のことが起きました。
「足がまったく動かない」と言って、救急車で搬送。
今度は「一過性脳虚血性発作」との診断。
そこから、ついに歩くことができなくなってしまいました。
トイレに行くときも、母が車いすで連れて行きます。
トイレの中のことは、まだ自分でできるのが救いだけれど、
「いつ行きたくなるか」がわからないので、
父を一人にしておくのがますます難しくなりました。
そして、父も母も6年前より、確実に歳を重ねています。
まさに、世間で言われる「老々介護」の状態です。
そんな中で、
近くに住んでいて、平日は比較的自由に動ける私が、
本格的にサポートに入ることになりました。
今までも、ちょこちょこ手伝ってはいたけれど、
今回はもう少ししっかり関わる必要が出てきたようです。
介護って、本当に家族によって、それぞれいろんなカタチがあると思います。
ここでは、私なりの介護のカタチを、
できるだけ自然体でつづっていけたらと思っています。
誰かにとって、ほんの少しでも参考になったり、
心が軽くなるきっかけになれば嬉しいです。

